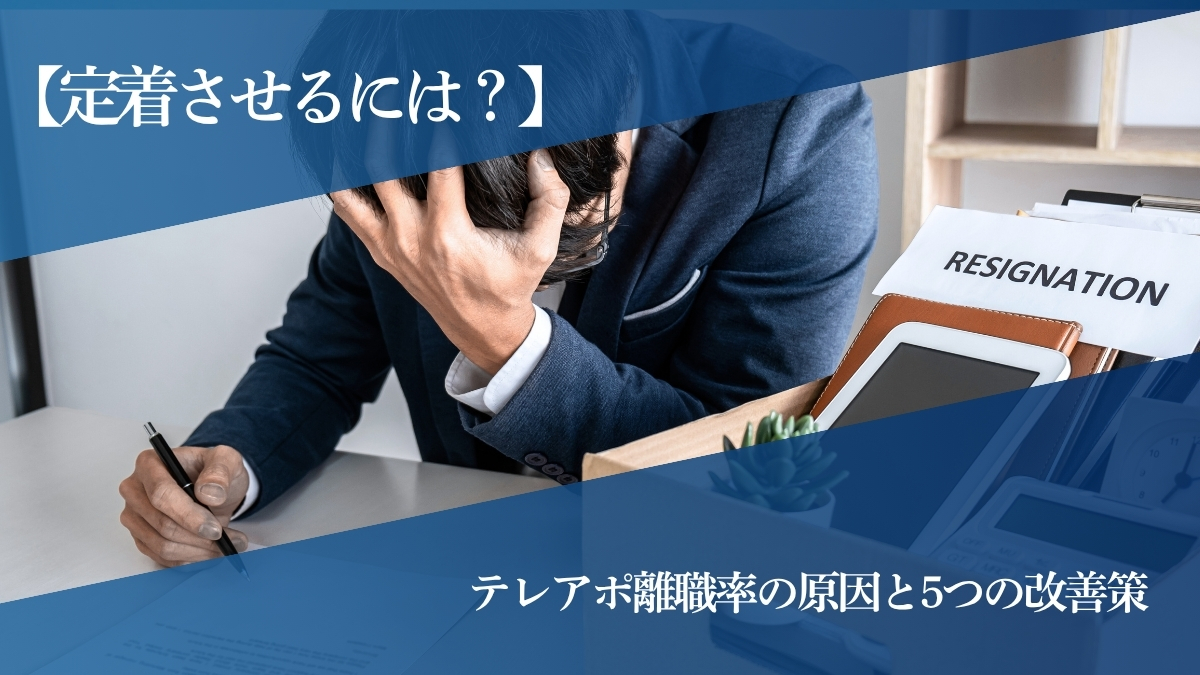「テレアポ担当を採用してもすぐ辞めてしまう…」
そんな悩みをテレアポ担当者の離職率の問題に対して頭を抱える企業の営業管理職や人事担当者は少なくありません。
テレアポは一般的なコールセンター業務とは異なり、企業の新規の顧客開拓を目的とした
“営業型の架電業務”で
| 「対応力より成果プレッシャーが大きい」
「営業スキルを問われる」 |
など、離職の要因もコールセンターとは性質が異なります。
さらに、成果への意識の高さやメンタル負担が定着率に大きく影響し、テレアポの離職率は非常に高いです。
なぜこれほどまでにテレアポ担当者の離職率は高いのでしょうか。
本記事ではテレアポ離職率が高い主な原因と、企業側でできるテレアポ担当者の定着率を上げる
育成・マネジメントのポイントを解説します。
テレアポ成功の全体戦略ガイド資料ダウンロード
BtoB特化型テレアポ代行サービス「グッドアポ」は、アポ“数”ではなく
“商談化・成約”に直結する質重視の営業支援を行っています。
成約率アップにつながるノウハウと成功事例をまとめたPDFを
今すぐ無料でダウンロード!
目次
テレアポ離職率が高い5つの理由
テレアポは、他の営業業務と比べても負担が大きく、短期間で辞めてしまうケースが多く見られます。
主な理由として、以下の5つが挙げられます。
想定外の精神的負担が大きい

テレアポ業務は担当者にとって精神的な負担が大きい仕事です。
慣れない電話対応でお客様に冷たくあしらわれたり、強い口調で拒絶されたりすると
誰でも大きなストレスを感じてしまいます。
オフィスでは電話越しに厳しい言葉を何度も浴びることもあり、成果が出ない日々が続くと
「自分は向いていないかも」と自信を喪失するテレアポ担当者も少なくありません。
こうした精神的プレッシャーの積み重ねが、テレアポの離職率が高い大きな要因になります。
厳しいノルマのプレッシャー

多くの営業職と同様に、テレアポにも数値目標(ノルマ)が課せられます。
例えば、新人であっても架電件数やアポイント獲得件数などの目標を追わねばならず
達成できない日が続くと強いプレッシャーを感じるようになります。
特にテレアポはマニュアルどおりに進めてもアポイントを取れる確率が低く、いくら電話を
掛けても成果が出ず上司から叱責されるという事態も珍しくありません。
高すぎるノルマに追われる環境では、努力が報われない無力感から自信を喪失し、精神的にも
追い詰められてしまいます。
研修不足と覚えることの多さ

テレアポ担当者が早々に辞めてしまう背景には、企業側の研修・教育体制の不十分さもあります。
テレアポ業務は想像以上に習得すべき知識やスキルが多く、商品知識、トークスクリプト、
顧客対応手順、CRMシステムの操作方法など新人が覚えることは山ほどあります。
しかし実際には、そうした十分な研修期間を設けられずに現場に配属されたり、上司や先輩の
フォローが行き届かなかったりするケースも少なくありません。
研修が中途半端で「何をどうすればいいか分からない」ままではテレアポ担当者の心は
折れてしまい、結果的に早期離職につながってしまいます。
将来のキャリアパスが見えない

テレアポ特有の悩みとして、将来のキャリアビジョンが描きにくいことも挙げられます。
テレアポ業務ばかりをしていて「このままで大丈夫だろうか」と不安を抱くテレアポ担当者は
多く、明確なキャリアステップが示されない職場ではモチベーションが低下しがちです。
将来性を感じられないテレアポ担当者は「この先続けても成長できないのでは」と早期に
離職してしまう傾向があります。
業務が単調で裁量も少ない

テレアポ業務は毎日決まったリストから電話をかけ続ける単調な作業の連続になりやすいです。
そこにやりがいや裁量の少なさを感じてしまう人もいます。
「自分の工夫で仕事を良くしよう」という余地も少なく、言われたスクリプト通りに
こなすだけでは仕事の手応えを得にくいものです。
こうした単調さや自主性の発揮しづらさもモチベーション低下の一因となります。
| テレアポ離職率が高い理由まとめ |
| ☑️ 想定外の精神的負担が大きい |
| ☑️ 厳しいノルマのプレッシャー |
| ☑️ 研修不足と覚えることの多さ |
| ☑️ 将来のキャリアパスが見えない |
| ☑️ 業務が単調で裁量も少ない |
以上のように、テレアポ担当者の離職率が高いのは、仕事自体のストレスフルな性質や
環境面の課題が大きく影響しています。
では、企業側としてテレアポ担当者の定着率を少しでも上げるためには、具体的に
どのような対策が考えられるでしょうか。次に、そのポイントを見ていきます。
テレアポ担当者の定着率を上げるための改善策
テレアポ担当者の離職を防ぎ、長く活躍してもらうために企業が取り組むべき施策をまとめました。
教育体制から評価制度、職場環境まで、総合的な見直しが重要です。
| 研修を充実させる |
| テレアポ配属前に十分な研修を行い、基礎知識やスキルを身につけさせることが肝心です。
ビジネスマナーや商品知識の習得から始まり、トークスクリプトの練習やロールプレイング OJTまで段階的にスキルを積ませる環境を用意しましょう。
特に入社直後の数ヶ月〜半年は集中的にフォローを行い、困ったときにすぐ相談できる体制を 整えることで、不安を解消し自信を持って業務に取り組めるようになります。 |
| ノルマ・評価制度を見直す |
| 過度なノルマプレッシャーをかけないよう、段階的に目標を設定できる評価制度に見直し
経験や習熟度に応じた現実的な目標からスタートさせましょう。
最初のうちは比較的アポイントが取りやすいリストから架電させ、成功体験を積ませてあげる 工夫も効果的です。
小さな成功を重ねて自信がつけば、徐々に高い目標にも挑戦できるようになり、結果的に本人の 成長意欲と定着率向上につながります。 |
| インセンティブや表彰制度の導入 |
| 社員のモチベーションを維持・向上させるために、評価基準を明確にして適切なインセンティブ報酬や
表彰制度を設けるのも有効です。
たとえばアポイント獲得数や電話対応品質などを公正に評価し、達成度に応じて報奨金や 表彰を与える仕組みを整えます。
努力が正当に報われていると感じられれば、「もっと頑張ろう」という意欲につながり 離職防止に寄与します。
ただしインセンティブの目標設定は無理のない水準にし、過度な競争やプレッシャーにならないよう 注意しましょう。 |
| キャリアパスを明示する |
| テレアポ業務を経験した先にどんな成長や役職が望めるのか、将来的なキャリアパスを社員に
示すことも大切です。
「◯年後には◯◯職にステップアップできる」といった具体的なロードマップを提示し テレアポで習得したスキルを活かして営業職やSVへ昇進できる可能性があることを周知します。
将来のイメージが描ければテレアポ担当者の不安が和らぎモチベーションが上がりますし 「この会社で頑張り続ければキャリアアップできる」という安心感が定着率の向上につながります。 |
| チームで支える職場づくり |
| テレアポは個人プレーになりがちな業務だからこそ、組織全体で支える風土を作りましょう。
理想は先輩社員がマンツーマンで指導したり、上司が定期的に1対1の面談を行ったりして 個々に寄り添ったフォローをすることです。
また発破をかけるばかりでなく、チーム全体で目標達成を目指すやり方も検討しましょう。
個人ノルマだけだと重荷になりがちですが、チーム目標を設定すれば、一人ひとりの 負担が軽減されストレスも減ります。
気軽に相談や悩みを打ち明けられる職場環境を整えることでが重要です。 |
以上のような施策を組み合わせて実践することで、テレアポ担当の感じる負担を減らし
成長しながら長く働いてもらえる可能性が高まります。
もちろん現場ですぐに全てを変えるのは難しいかもしれませんが、できるところから少しずつでも
改善を図ることが肝要です。
テレアポ代行サービスの活用も
それでも「自社内でテレアポ担当を育成・定着させるのが難しい」と感じる場合は
テレアポ業務を専門の外部サービスに委託することも選択肢に入れてみましょう。
当社の提供するテレアポ代行サービス「グッドアポ」では、BtoB商談獲得のプロフェッショナルが
専任アポインターとして常駐し、クライアント企業のアポイント獲得業務を代行しています。
経験豊富なスタッフが最初から成果追求にフル稼働するため、テレアポ担当者の育成にかかる
時間やコストを他の重要業務に振り向けることができます。
何より、アウトソーシングを活用すれば「せっかく採用・研修した新人がすぐ辞めてしまう」
リスクから解放されるのが大きなメリットです。
テレアポ代行を利用すればオペレーターが途中で退職する心配はなく、安定してアポイント
取得活動を継続できます。
自社内にテレアポ専任者を抱える負担や不安を減らし、確実に成果を出すためにも、
テレアポ代行の活用は有効な解決策と言えるでしょう。
「アポ率を上げたい」「成果が伸び悩んでいる」など、
テレアポに関するお悩みを、グッドアポの専門担当が
無料で診断します。
現場データに基づいた改善提案で、最短で成果へ導きます。

まとめ
以上、テレアポ担当者の離職率が高い理由と、その定着率を上げるためのノウハウをご紹介しました。
テレアポの離職率が高い背景には様々な要因がありますが、企業側の工夫次第で働きやすい環境を整え
テレアポ担当者の離職を防ぐことは十分可能です。
社員の定着率が上がれば
| テレアポ業務の生産性も向上し、ひいては営業成績の安定にもつながります。 |
「雇ってもすぐ辞められる…」という悪循環に悩んでいる場合は、本記事で取り上げた対策をぜひ
取り入れてみてください。
それでも社内での対応が難しいときには、プロに任せるテレアポ代行サービスの利用も検討し
安定したアポイント獲得体制の構築を目指しましょう。
テレアポ担当者がイキイキと、活躍できる職場づくりを応援しています。