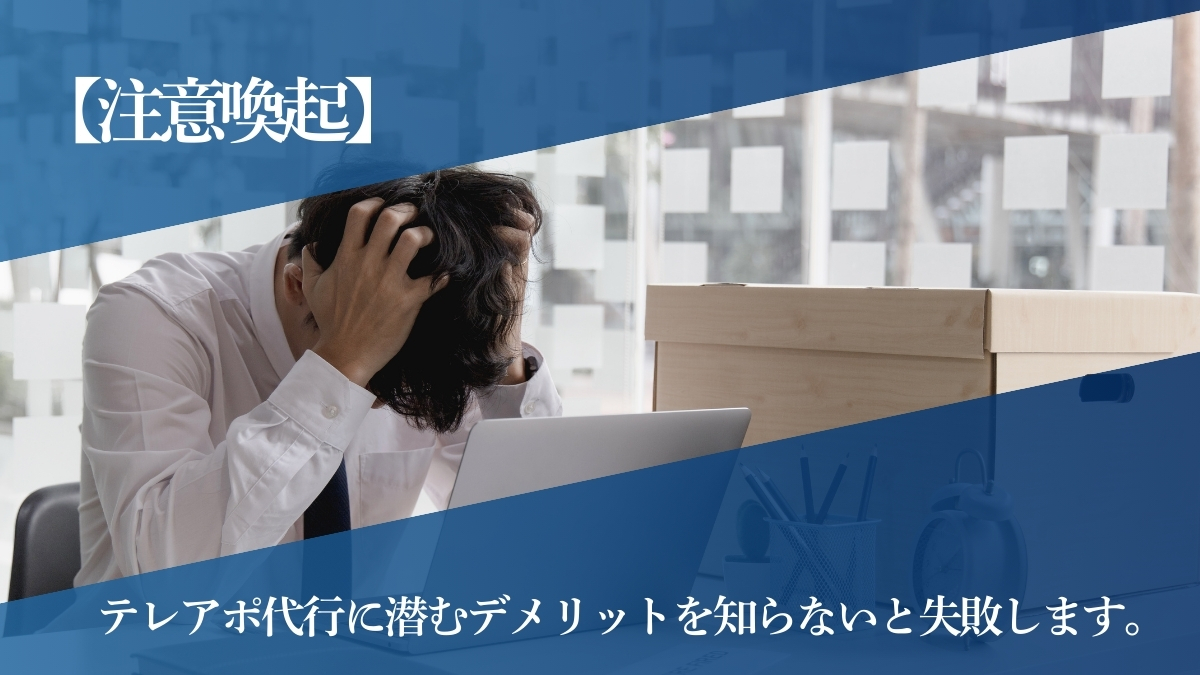「テレアポ代行にはメリットもあるけれど、デメリットも多いと聞く…」
「外注したいけれど、本当に成果が出るのか不安…」
「アポは取れたのに、なぜか成約にはつながらなかった…」
そんな悩みや疑問を感じたことはありませんか?
テレアポ代行は、自社の営業リソースを補い、新規開拓を加速できる強力な手段です。
しかしその一方で、「思ったような成果が出なかった」「丸投げしたら失敗した」といった声も多く、成功と失敗の
差が出やすい仕組みでもあります。
こうした差が生まれる背景には、「外注=成果が保証されるもの」ではなく、そもそも外注という仕組みそのものが持つ
構造的な弱点が影響しています。
たとえばアポの質が担保されにくいことや、営業体制と連携しづらいことなどが原因です。
とはいえ、これらは「仕組みとしてどう使うか?」を理解し、戦略的に設計できれば回避できるリスクでもあります。
この記事では、テレアポ代行の主なデメリットを整理した上で、「どう使えば損をせず、成果につなげられるのか?」
そのポイントと考え方をお伝えします。
外注を検討している方も、過去にうまくいかなかった経験がある方も、テレアポ代行を使いこなすためのヒントとして
ぜひ参考にしてみてください。
テレアポ成功の全体戦略ガイド資料ダウンロード
BtoB特化型テレアポ代行サービス「グッドアポ」は、アポ“数”ではなく
“商談化・成約”に直結する質重視の営業支援を行っています。
成約率アップにつながるノウハウと成功事例をまとめたPDFを
今すぐ無料でダウンロード!
目次
テレアポ代行に潜む4つのデメリット

テレアポ代行を外注する際には、「アポが取れる=成果が出る」と思い込みすぎるのは危険です。
代行を導入すれば一見ラクに見えますが、安易に任せてしまうことで、かえって営業効率や売上に悪影響を与える
ケースも少なくありません。
ここでは、外注を検討する際に把握しておきたい主なテレアポのデメリットを4つご紹介します。
1. アポイントの質が担保されにくい
→成果を“アポ件数”で評価する構造のクセ
多くの代行会社では「アポイント件数=成果」とされやすく、“数”を稼ぐことが目的化される傾向があります。
その結果、本来であれば商談や成約に結びつく“質の高いリード”よりも、「とりあえず会ってもいい」と言っただけの
企業(実際はニーズも導入意欲もない)といった温度感の低いアポが増えてしまうリスクがあります。
特に成果報酬型の場合、「アポさえ取れれば成果」になるため、内容よりも件数が優先されがちです。
そうなってしまうと、 営業担当が商談しても成約に至らず、現場のリソースを浪費するだけの空アポが増えてしまうという
デメリットがあります。
2.自社の営業体制との連携不足によるミスマッチ
→分業構造ゆえの“プロセス接続リスク”に注意
テレアポ代行は、営業活動の「入口」だけを担う部分委託の仕組みです。
つまり、代行はアポ獲得まで、その後の商談・クロージングは自社という「分業設計」で動くことになります。
ところがこの構造、両者が密に連携していなければすぐに破綻してしまいます。
|
といったプロセス接続の設計が曖昧だと、「アポは取れたけどニーズが全然違った」「提案したらそんな話聞いてない」
と断られたというようなアポのズレや情報ギャップが頻発し、成果につながらなくなりにくくなってしまうという
テレアポのデメリットがあります。
3. 丸投げでは「アポは取れたけど成約ゼロ」に陥りやすい
→“任せきり構造”が生む分断と放置
代行導入時の典型的な失敗パターンがこれです。
つまり、アポさえ取ってくれればOKだから… ▷▷▷完全に丸投げした結果、成果ゼロという構図です。
これは、テレアポ代行という仕組みがそもそも「受け身に動く構造」であるためです。
スクリプトの改善、リストの見直し、アポ後の動きなど、発注側が設計・関与しなければ代行側は自走しません。
外注という仕組みを「ただ任せれば勝手に動くもの」と捉えてしまうと、アポは増えても受注ゼロという悲劇を
招くことにな李、こちらもテレアポのデメリットと言えます。
4. 自社にノウハウが蓄積されない
→“知見が社外に残る”外注の宿命
もう一つ見落とされがちなのが、社内に営業ノウハウが残らない問題です。
テレアポの成果や失敗の中には、本来であれば社内で蓄積すべき学びが数多く含まれています。
|
これらは貴重な営業資産であるにも関わらず、フィードバック体制がないまま代行任せにしてしまうと、すべて社外に
置き去りになります。
結果、いつまでたっても自社でテレアポの型が作れず、「外注なしでは回らない体制」から抜け出せなくなってしまいます。
こちらもテレアポのデメリットと言えるでしょう。
それでは、なぜこのようなリスクが発生してしまうのでしょうか?
テレアポ代行にデメリットが生じる原因

ここまでお伝えしたようなテレアポ代行のデメリットは、代行会社側の問題だけではなく、
発注する企業側のスタンスや準備不足によっても引き起こされることがあります。
ただしここで重要なのは、「発注側の姿勢が悪い」と単純に責任を押しつけることではありません。
実はその背景には、外注という仕組みそのものの構造的な特性が大きく関係しています。
前章でも何回かお伝えしたとおり、テレアポ代行は基本的に「受け身の構造」です。
発注企業がしっかりと情報を渡し、意図を共有し、フィードバックしていく前提で初めてうまく機能する仕組みです。
しかし「代行に依頼すれば、あとは全部やってくれるだろう」と考えて任せきってしまうと、この構造はかえって
発注側の課題を顕在化させてしまいます
例えば以下のようなよくある発注側の落とし穴は、いずれも構造を理解せずに外注を扱った結果とも言えます。
|
|
|
|
このように、テレアポ代行の失敗には任せる側の設計力も大きく関わってくるのです。
重要なのは、「外注=楽ができる仕組み」ではなく、「外注=適切に活用すれば営業力を拡張できる仕組み」であるという
理解です。
仕組みのクセを理解し、それを自社にとって活かせる設計にできれば、外注でも高い成果を出すことは十分に可能です。
しかし状況によってはテレアポ外注自体が適さないケースもあります。
「テレアポ外注をおすすめしないケースとは?失敗しないための判断ポイント」
上記の記事でも解説しているように、まずは自社のサービスや営業体制を見直し、
適切な手法かどうかを判断することが大切です。
「代行に任せたのに成果が出ない…」
その原因、実は“設計不足”かもしれません。
それでも代行を使うべきケースとは?

ここまでテレアポ代行のデメリットやその原因を見てきましたが、条件次第ではテレアポ代行は
非常に有効な手段となります。
次のようなケースでは、リスクを踏まえてもテレアポ代行を外注するメリットがデメリットを上回るでしょう。
小規模で専任のテレアポ担当者がいなかったり、電話営業のスキルが社内になかったりする場合、プロの代行に任せる価値は大きいです。教育や経験を積む時間を買うつもりで外注し、その間に社内リソースはコア業務に集中できます。 |
インサイドセールス的な役割を外注し、自社の営業チームは提案や契約締結など後半のフェーズに注力するパターンです。 これにより営業担当者の生産性が上がり、限られた人員でも 効率的に新規開拓とクロージングを両立 できます。 アポイント獲得と商談成立の役割分担を明確にすることで、全体の営業効率が向上するでしょう。 |
自社だけでは手が回らない件数のリードに素早くアプローチしたい、新規事業や新エリアで試験的に市場開拓したい、といった場合も代行の活用がおすすめです。 経験豊富な代行業者なら 即戦力 として稼働してくれるため、内製でゼロからチームを育成するより圧倒的にスピーディーに成果を期待できます。 タイムリーな営業活動が求められるシーンでは、外注をうまく使うことでビジネスチャンスを逃しません。 |
契約単価の高いBtoB商材であれば、少ない成約数でも十分な売上インパクトが得られるため、テレアポ代行との相性は良好です。 例えば年額数百万円規模のサービスなら、仮に毎月数件の契約が取れれば 費用対効果はプラス になります。 一方、低単価商材だと大量のアポ・受注が必要になるため外注コストに見合わないケースもあります。 つまり 高単価な商材ほどテレアポ代行を使うメリットが大きい と言えるでしょう。 詳しくはこちらのブログをご覧ください:t-mark.info |
このような状況に当てはまる場合、テレアポ代行の活用は十分検討に値します。
条件次第では自社内で賄うより効率良く成果を上げられる可能性が高いです。
では、テレアポ代行のデメリットを避けて成果を上げるには具体的にどうすれば良いのでしょうか?
次章で解決策を見ていきましょう。
テレアポ代行で失敗しないための解決策

テレアポ代行を効果的に活用し、失敗を防いで成果に繋げるためのポイントを押さえておきましょう。
1自社に合った優良な代行パートナーを選ぶ。
価格だけでなく実績や業界知識、提案力を重視し、単に電話をかけるだけでなく伴走型で支援してくれる企業を選定します。
自社の商材やターゲットを理解して戦略提案してくれる代行会社であれば、質の高いアポ獲得に期待できます。
さらに、トークスクリプトや通話録音を共有してもらえる会社であれば、アプローチ内容の透明性が高く安心です。
2丸投げにせず、密な情報共有とフィードバックを行う。
外注後も定期的にコミュニケーションを取りましょう。
リストの反応やアポの結果を共有し、トークスクリプトの改善やターゲット見直しなど常にPDCAを回すことで、
精度を高め続けることができます。
例えば週次で定例ミーティングを行い、結果報告と課題共有をすれば、お互い認識を合わせながら改善を進められます。
3アポイント後の営業フローを事前にすり合わせておく。
テレアポ代行会社任せにせず、取れたアポイントを自社営業で確実に活かせるように準備が必要です。
代行会社から得たリードは、商談設定後のフォロー(見込み客の温度感に合わせたアプローチや提案資料の準備など)
を自社でしっかり行い、商談から契約への転換率を上げましょう。
代行会社によってはアポ後のフォロー方法も含めてアドバイスしてくれる場合があります。
4KPI設定は「アポ数」より「質と成約率」を重視する。
単にアポイント獲得件数だけを目標にするのではなく、その先の商談化率や成約率を評価指標に含めます。
「アポは取れたが契約ゼロ」という事態を防ぐには、アポの件数以上に内容(見込み度合いや決裁者かどうか等)を重視し
費用対効果を上げることが重要です。
※テレアポの費用対効果については当社ブログ記事「そのテレアポ、費用対効果出てますか?アポ数より質を重視すべき理由」
も参考になります。
5契約形態やコストを事前にシミュレーションする。
成果報酬型や固定報酬型など、テレアポ代行にはさまざまな料金体系があります。
それぞれメリット・デメリットがあるため事前に試算し、期待する成果に見合う予算かを確認しましょう。
費用対効果の視点を持つことで「高い費用を払ったのに成果ゼロ」といった失敗を防げます。
上記のポイントを踏まえ、外注先とは「営業パートナー」として二人三脚で取り組むことが成功のカギとなります。
グッドアポは営業パートナーとして伴走支援

このブログで何度も伝えている通り「テレアポ代行だけ頼めばあとは任せて安心」という考え方は危険です。
逆に言えば、発注側が主体的に関わりさえすればテレアポ代行は強力な武器になります。
グッドアポでは、たとえ外注であっても貴社の営業パートナーとして伴走する体制を整えており、単なるアポイント数の
提供で終わらせません。
具体的には、アポイント取得のためのトークスクリプト改善やリスト戦略の見直しはもちろん、獲得したアポ後の
商談フロー設計まで支援し、「アポは取れたが成約ゼロ」という状況を防ぎます。
テレアポ代行のプロとして案件化まで見据えた提案を行うため、外注によるリード獲得がそのまま受注増加に直結
しやすいのが強みです。
実際にグッドアポではテレアポから最大成約率53%を達成した事例もあります。
「任せきりで自社は何もしないでいたい」というスタンスの企業様とは相性が合わない場合があります。
グッドアポはあくまで伴走型で共に走るパートナーですので、自社も積極的に改善に取り組む意思のある企業様にこそ
価値を提供できるサービスです。

まとめ
テレアポ代行は使い方次第で強力な新規開拓手段になりますが、丸投げでは思うような成果に繋がりません。
「アポイント数をただ増やす」のではなく「商談・成約につながる質の高いアポイントを取る」ことが重要です。
そのためにはターゲティングやスクリプトの最適化など、パートナー企業と一緒にPDCAを回し続ける姿勢が欠かせません。
外注先を信頼できる営業パートナーと位置づけて自社も主体的に取り組めば、テレアポ代行の効果を最大限に発揮できるでしょう。
「アポは取れるのに肝心の受注に至らない…」
「テレアポ代行を利用中だが、このままで良いのか不安…」
「自社に合ったテレアポのやり方を提案してくれる会社にお願いしたい…」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひグッドアポにご相談ください!
営業代行のプロが貴社の課題をヒアリングし、最適なテレアポ戦略をご提案いたします。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。